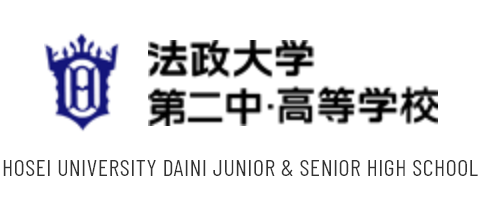人間環境学部クラス
人間環境学部クラスの3学期授業は、「持続可能性」を大きなテーマとして、「問題意識の育成」と「大学での学びの構築」をテーマに、付属校ならではの高大連携教育として多彩な取り組みを行います。
校内での取り組みでは、班体制を作り、研究発表に向けた取り組みを進めていきます。また、ゲスト講師による特別講義やフィールドワークも積極的に実施をする予定です。
集大成となるのが、研究発表をおこなうプレゼンテーションです。テーマごとに編成された各班が、それぞれの問題意識に基づき調査・研究をおこなった成果を発表します。
2024年度 人間環境学部クラスの取り組み
取り組み その1
人間環境学部クラスではプレゼン大会に向けて、各班の研究テーマの現状認識、問題点を整理しながら、各班で研究テーマを設定し、テーマの現状認識、問題点を整理しながら、班、個人としての「主張」を論ずることができるよう討議を進めています。
これらの貴重な体験を元に、「持続可能」を観点として、さらに各班の研究発表の準備を進めてほしいと思います。
取り組み その2
人間環境学部クラスではプレゼン大会に向けて、各班の研究テーマの現状認識、問題点を整理しながら、レジュメ、パワーポイントの作成をしています。また、週に1度フィールドワークを実施し、体験を通してさまざまなことを学習していきます。
1月21日は、「向ヶ丘遊園跡地保全運動と生田緑地」をテーマに、向ヶ丘遊園の緑を守り、市民憩いの場を求める会(遊園の会)の方々の案内のもと、生田緑地内を踏査しました。今年度は、人間環境学部、キャリアデザイン学部と合同の総勢60名の大規模FWとなりました。まず、遊園の会事務局長の松岡嘉代子さんによる講義を全体で受講しました。「人」と「自然」が持続的に共生するための開発とは何かについて、生徒たちは真剣に耳を傾けていました。その後の向ヶ丘遊園跡地をめぐる踏査では、山道を歩く場面もあり、生田緑地に残っている自然と在りし日の遊園の跡を大いに体験でき、天気にも恵まれ緑地散策を満喫していました。
1月26日は、鎌倉フィールドワークを実施しました。事前学習では、鎌倉が古都保存法発祥の地であること、そのきっかけとなった八幡宮裏山(御谷の山)のナショナルトラスト運動を学習しました。フィールドワークでは、八幡宮、切り通し、寺院・神社仏閣、やぐらを通るルートを生徒たちで考え、各班でコース設定してもらいました。当日は良い天気に恵まれ、歴史と共生する街として鎌倉を捉えることができました。
2月6日は、国際協力とSDGsをテーマに、JICA横浜に伺い、日本国内の民間企業が海外で、どのような事業に取り組んでいるか、国際協力とSDGs、また、NPOや市民団体が行っている国際協力活動について学習しました。特に発展途上国に対して、各班で取り組んでいる研究テーマを世界に目を向けたとき、どのようなSDGsについての観点で生かせるのか考えることができたようです。
取り組み その3
3学期の取り組みの一つの到達点として、2月20日にプレゼンテーション大会が実施されました。発表は、フィールドワークなど研究調査を通して議論し、問題点と解決法をパワーポイントにまとめたもので20分程度発表しました。
各班、それぞれ工夫をこらして、テーマの現状、問題点、解決策について分析・提案し、お互いに質問して議論しあうことができました。当日は、法政大学人間環境学部から藤田研二郎先生にお越しいただき、各班に向けて講評とアドバイスをいただきました。7週間という短い取り組みでしたが、アドバイスいただいた点は、きっと大学での学びに繋がるかと思います。
人間環境学部に進学する生徒たちには、これまでの「出会い」と「学び」の経験を振り返ったうえで、4月からの新しい学生生活に邁進してほしいと思います。
1班:武蔵小杉をより住みやすい街に
2班:食卓から見る貧困~日本の子どもたちの現実と未来~
3班:管理職におけるジェンダーギャップ~どうすれば女性リーダーを増やせるのか~
4班:その教材、まだ舞える。世界を変える教材リユース
5班:『脱!過剰包装』
6班:コーヒーと「いのち」
7班:災害時も安心した暮らしを〜避難所を増やす鍵は空き家!?~
8班:一家に一台、小水力発電