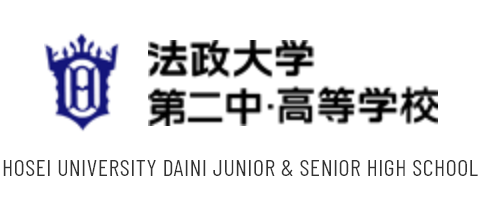文学部 地理・史・日本文学科クラス
2024年度の文学部地理・史・哲学・日本文学科は,伊丹聡一朗・濱口裕介・雨宮康弘・長瀬由紀峰・堀田匡秀の5名が担当します。クラスは地理・史・哲学科と日本文学科とに分けて実施します。
方法論は学科それぞれで異なりますが,各特色を考慮しつつ他の方法論を学ぶ機会として位置付けていきます。特講やフィールドワーク,講師や卒業生による講演会も予定しています。
2024年度 文学部 地理・史・日本文学科クラスの取り組み
取り組み その1
【哲・地理・史学科】
3学期の取り組みとして,まず,各学科の方法論について学び,大学カリキュラムについて知り,レポート・論文作成の方法などについても理解を深めました。加えて,外部講師として山口清貴氏に講演をお願いしました。ご多用のところ,お引き受けいただき,ありがとうございました。
また,FWとして「国立歴史民俗博物館」,「禅文化歴史博物館」,「世田谷ボロ市通り」,「大谿山 豪徳寺」,「鶴岡八幡宮」,「円覚寺」,「建長寺」などに行きました。当日,解説してくださった学芸員の方に御礼申し上げます。
なお,プレゼンテーション大会に向けて,地理学科は「人文地理」と「自然地理」の二つのグループにわけて一グループ一報告,史学科と哲学科は一人一報告として実施しています。


【日本文学科】
日文クラスは、〈文学〉〈言語〉〈文芸〉といった大学でのコース別の学びを想定して各分野の特色を学び、大学での学びに繋がる土台の構築を進めています。また、各学科の担当者の専門性を活かした授業(特講)を展開しています。特講の内容は、文学研究の方向性について、古典分野、日本語圏の文学について、サブカルチャー論など幅広く展開しています。
また、FWも実施しています。この間に実施したものは以下の通りです。
◆国立国会図書館見学(普段は見られないバックヤード見学と職員の方からの解説)
◆佐倉城址・国立歴史民俗博物館見学(哲・地理・史学科クラスと合同実施)
(※本ページの画像はFW時のものです。)
1月21日(火)には「付属校事前オリエンテーション」が法政大学市ヶ谷キャンパスで実施されました。
・尾谷昌則教授 テーマ:言葉は変わるよ、どこまでも~言語変化の多様性~
オリエンテーションを通して、「大学生」という意識を様々な意味で深めることができました。
特講やFWの他にも並行して、プレゼン大会に向けて報告テーマを設定し、報告のアウトラインの作成にも取り組んでいます。次回はそれらの内容含めて(一部)お伝えしたいと思います。
国立国会図書館
国立歴史民俗博物館
佐倉城址公園見学に向けて
特講の一コマ
取り組み その2
【哲・地理・史学科】
付属校事前オリエンテーションが行われました。
▽地理学科:佐々木達
▽史学科:齋藤勝
▽哲学科:佐藤真人
市ヶ谷キャンパスで「大学での学び」について学んできました。
また,外部講師の大貫義久さんに「哲学」の授業をお願いしました。授業では,「大学での哲学」について触れることができました。ご多用のところ,ありがとうございました。
FWは,「千年伊勢山台遺跡(橘樹郡家跡)」・「影向寺遺跡」,「府中市郷土の森博物館」・「大国魂神社」・「国史跡武蔵国府跡(国衙地区)」・「JRA博物館」,「神保町」・「法政大学発祥の地」・「ニコライ堂」・「史跡湯島聖堂」・「神田明神」に行ってきました。
さらに,法政大学史学科の土橋楓さんに「大学での学び」について,法政大学哲学科の水嶋桜菜さんに「大学生活」について,法政大学地理学科の岩田真央さんに「地理」についてお話をしていただきました。お忙しいなか,ありがとうございました。
そして,プレゼン大会に向けての準備も進んでいます。リハーサルを経て来週のプレゼン大会を向かえます。
【日本文学科】
3学期の取り組みが始まり、一か月以上経ち、中高の入試期間の休みも終えてすでに終盤戦に突入です。クラスでは、プレゼン大会に向けた準備と並行しながら、施設見学やフィールドワーク(FW)で実際に現地に足を運びました。
〔この間実施した施設見学・FW〕
◆横浜(山手文学散策・中華街)
当日は海の見える丘公園に集合し、そこから神奈川県立近代文学館、大佛次郎記念館を必須とし、その他周辺の任意の場所での文学散策をし、横浜中華街集合で解散するという流れで実施しました。
最後に、プレゼンテーション大会についてですが、日本文学科クラスは、2月19日(水)に実施します。当日は、大学から先生に来校いただいての実施となります。
〔発表予定のタイトル一覧〕
- 古事記『黄泉国訪問神話』より
- かがみの孤城から読む不登校問題
- 芥川賞受賞作品から見る現代社会の反映
- 「愛」と「恋」の違い
- 谷川俊太郎と孤独
- 希望の文学
- 物語が映し出す現実
- YOASOBIの歌詞を解く
- 村上春樹の小説について
- オノマトペの有用性
- 『山月記』の価値
- 日本での虹の受容
- 児童文学においてなぜ戦争をテーマにするのか
- 小説・物語はなぜ面白いのか
- 「辻村ワールドすごろく」における秋山一樹の存在
- 中島敦の自我への執着
- 「こころ」における襖の意味
取り組み その3
【哲・地理・史学科】
プレゼンテーション大会が行われました。
法政大学地理学科から佐々木達氏,史学科から宇都宮美生氏,哲学科から内山真莉子氏,にお越しいただき,各テーマに対するコメントをいただきました。ご多用のところ,ありがとうございました。
以下,報告テーマを紹介いたします。
------------------------------
【地理学科】
・鎌倉の外国人観光客に対する防災対策と地域住
・地球温暖化に対する川崎市の責任と役割
------------------------------
【史学科】
・鎌倉幕府の成立時期を考える
・栄西と茶
・松本藩における北塩専売政策の成立理由
・プッチーニの遺作『トゥーランドット』と未完の謎
・映画の歴史と人々との関わり
・邪馬台国の論争~遺跡から考える~
・占守島の戦いから考える北方領土問題
・モンゴル帝国の海運の変化と影響
・『コンスタンティヌスの生涯』における異教弾圧とその実像
------------------------------
【哲学科】
・ラッキーを掴み取るには
・幸福探求〜過去から未来,幸せのその先へ〜
・生きることの矛盾と宿命〜実存主義における「自由」と「孤独」〜
・人は歴史から何を学ぶの
・悩みとの向き合い方について
・恐怖の本質〜娯楽として楽しまれる恐怖とは〜
・男女共同参画社会の姿と日本の実状を考える
------------------------------
生徒は,報告と大学教員からのコメントを受けて,「まとめの論文」作成になります。
これからの大学生活に期待いたします。
【日本文学科】
第1クールの最後を飾る“プレゼンテーション大会”が2月19日(水)に終了しました。当日は、法政大学から坂本勝先生にお越しいただき、生徒たちは緊張しながらも各自が調査分析した成果を発表しました。保護者の方々にもお越しいただき、充実した大会となりました。
また、同日午後には早瀬太亮さんに来校してもらい、OB講演を実施し、大学生活全般に関する話をしていただきました。また、早瀬さんは、昨年度の「第21回全日本学生落語選手権 策伝大賞」で大賞の策伝大賞を受賞した学生落語家でもありますので、落語(演目:夢八)も披露してもらいました。生徒たちは、来る大学生活のリアルに触れて思いを新たにし、また、落語という伝統話芸に触れてその面白さを体感する様子が印象的でした。
今後は、第二クールとして、今回のプレゼンを論文としてまとめ上げていくこととなります。(この「まとめの論文」における優秀論文は「まとめ集」に掲載される予定です。)年明けから始まった「三年三学期」の取り組みもこの第二クールで終了となります。