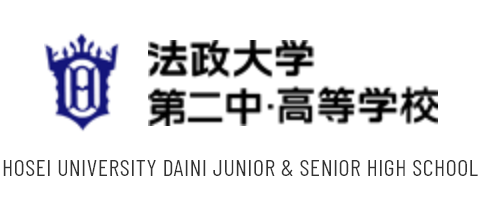授業
国語
自ら学ぶ力、言葉、表現を学ぶ
高校では、「論理的な読解力」の養成に主眼をおきながら、「論理的な思考力・表現力」の獲得までを視野に入れたカリキュラム編成を行っています。これらの力はあらゆる勉学の基礎となると同時に、筋道を立ててものを捉えていく時や他者とつながりながら考えを深め伝え合っていく時に求められる、人間として不可欠な力であると言えるでしょう。また、民主的社会の形成者に求められる言語能力・態度であるとも言えるでしょう。新教育課程では、1年次に「現代の国語」「言語文化」、2・3年次には「文学国語」「古典探究」を履修し、「なぜそう読めるのか」を明確化した学習を行っていきます。特に「書くこと」や発表学習を多く取り入れ、認識の拡がり・深まりを目指しています。
社会
幅広く学び、探究活動やグループワークを通じて発展的学力の形成へ
高校では、中学校までの学習を基礎に、大学で学び続けるために必要な、発展的な学力の形成を目指します。1年次に「地理総合」・「公共」、2年次に「歴史総合」・「政治・経済」、3年次に「世界史探究」・「倫理」・「日本史探究」(文系のみ)というように幅広い分野の学習を積み重ねます。そして通常であれば「地理歴史科」と「公民科」で異なる教科として学習するものを同じ「社会科」として関連させながら同時に学習することも大きな特徴です。
また多くの科目では地図、統計、法令・判例、史料など様々な資料の読解作業に取り組み、「公共」や「日本史探究」ではフィールドワークによる調査活動もおこなうことで、探究する力を身に着けます。さらに「公共」や「歴史総合」での発表学習、「倫理」での討論学習など、多くのグループワークを通じて仲間と協働して成果を生み出す経験も大切にしています。
数学
数学を積極的に活用する力を養う
数学の授業は1年・2年次に基礎教養として位置づけられている「数学Ⅰ」「数学A」「数学Ⅱ」を学び、3年次からは志望進路ごとに分かれて学習します。
具体的には文系学部を志望する生徒は「数学Ⅰ」「数学A」「数学Ⅱ」の演習を通して更なる定着を図ります。また「数学B」も取り組みます。
理系学部を志望する生徒は「数学Ⅲ」「数学B」を中心に学習することになります。理系の生徒はさらに「数学C」が必修となり、大学での数学の講義がきちんと理解できるだけの学力が身につくようカリキュラムが組まれています。
理科
実験・実習から自然の本質を知る
高校では1年生で地学基礎と生物基礎、2年生では化学基礎と物理基礎、3年生では科学と人間生活という構成になっています。理科の目標は「自然科学の基礎的知識(基礎的事実や法則および方法)を学習し、そのことを通じて科学的自然観を養い、自然や社会に対する豊か洞察力を身につけ、諸課題の解決に向けて主体的に行動できる人間を育てる」ということです。私たちは理科でつけるべき力は理系だけに必要なものであるとは考えません。科学は自然科学から発祥し、現代の発展を支える基本的なものです。理科を学ぶことによって、そのようなものの見方・考え方を身につけ、生きていく中で全ての対象を科学的な目で見て欲しいと考えています。
美術
表現する力と教授する力の育成
美術では絵画およびデザイン分野を扱いますが、実技を中心とした授業を通して、自分の思いを豊かに、そして個性的に表現できる力の育成を目指すとともに、他者の表現を受け取る力の獲得も大切な目標としています。
表現においては、それを支える技術の習得も欠かすことのできない内容として押さえますが、実生活の反映としてのリアリティの追求を目指します。
また、人類の生み出した芸術、文化や他者の表現に触れ、異質なものも受け入れ、美しいものを美しいと感じることのできる、しなやかな感性を磨きます。
音楽
Music is Magic
本校の音楽科では、「自分で作曲し、それを自分で演奏する」という、自作・自演発表会を最終目標に、2年の3学期にグループで取り組みます。ここでは多様な楽器編成での演奏が聞けて、非常に興味深いものがあります。この取り組みに向けて、1年から実践的にも理論的にも系統立てて学んでいくことになります。
実技は、主に歌唱と器楽(アルトリコーダー)に取り組んでいます。独唱(奏)、デュエットを中心に、自己表現力の向上を目指し、アンサンブルへの理解を深めていきます。理論では、「楽譜を読む・書く」という観点から、初歩の初歩から学習し、作曲法や和音の学習まで進めていきます。更に音楽史や鑑賞では、作曲家の時代背景も学び、作品の持つ魅力を深く追求することを目標にしています。
保健体育
正しいスポーツ観・健康観を実践で養う
保健体育科では、大筋群・呼吸(循環)器系・神経系の発達を目指して授業を展開しています。あらゆる競技を体験しながらバランスの取れた体力を獲得するためのカリキュラムが用意されています。
個人スポーツでは、個々の課題克服に向けて取り組み、集団的なスポーツでは他との協調やリーダーシップを学びます。そこで獲得された能力が実生活に反映できるような指導を心がけ、単に勝ち負けだけにとらわれない正しいスポーツ観の確立を目指しています。また、年一度の体力測定のデータを基に自己の体力分析を行い、高校3年間はもとより、卒業後においても体力を維持向上させるための学習にも取り組みます。
保健学習では、生涯にわたって健康に社会生活を営むため、身体・精神・環境・集団に視点をあてて学習します。
情報
客観的な認識能力と情報発信能力を培う
情報技術の発達とそれが人々の暮らしに与えた変化、メディアリテラシー、情報技術が引き起こした環境問題等「情報化社会」に関わるテーマを選び、年間を通して調査、研究、発表をしていきます。その過程を通じ、文献検索のやり方や簡単な統計処理など情報の収集・加工・発信のプロセスを学びます。多様な情報の行きかう現代社会の中で、事実を客観的に認識する力を培うとともに、自ら考えを積極的に表現できる、情報発信者としての基礎的な力を身に付けます。
家庭
生活の身近な題材から社会と自分を考える
高校の家庭科では、自分の生活を出発点にして授業を展開します。「女らしさ、男らしさは必要か」「食品選択と環境問題のつながり」「成年になるために必要なこととは」などを様々な手立て、角度から考えます。
授業や課題では、ディベートやインタビュー課題など多様な他者の考えにふれる機会をつくり、自分の価値観をゆさぶり広げます。そして、これからの自分の生き方と結びつけていきます。
多様な価値観をもつ人や、社会や世界とのつながりを意識できる生活者になりましょう。授業を創るのはみなさん1人1人です。
英語
総合的な英語力を習得する
3年間の英語学習を通して「語彙力」「文法力」「読解力」を定着させ、「英語による自己表現力」を育成することを目標にしています。1・2年次には日常用いられる基本英語をしっかりと使えるレベルにまで定着させ、3年次にはその力を大学での学問研究に対応できるレベルにまで発展させます。学習態度や学習方法を具体的に提示し、わかりやすい学習の目安を与えながら、生徒が「自分の間違いから学べる」ようになることを重視しています。
1クラスを2分割して授業を行う分割授業を1・2年次は週3時間(英文法と英語表現)行い、基本英語を自分で使えるレベルまで定着させます。英語表現の時間は外国人講師の指導の下、付属校ならではの「英語による自己表現力」を追求します。
また年2回、TOEIC Bridge®を全員が受験し、積み上げられた英語の総合力を定期的に測る他、その対策としてオンライン上に対策教材をアップし、どこにいてもTOEIC Bridge®の学習がはかどるようにします。